自分で作るの大好きな皆様こんにちは!木材をきれいに見せるため又は経年劣化を抑えるためニスで仕上げの塗装をしてみようと考えた事はありませんか?
私は、せっかく製作したのだから保護したいなと思いホームセンターに行ってみましたがニスも沢山の種類があって非常に悩んだ結果塗料同士の塗り合わせで失敗することも度々ありました。
ここでは油性ニスを使ってそれがしが自ら実践した手法、使った道具、塗料、注意点などを解説します。
✓本記事のテーマ
この記事を読めば大きな間違いをせず油性ニス仕上げ塗装が出来ます。

これら当HPの情報は、管理人が情報を集め徹底的に実践した中での品質、結果になりますので記事を読んで作業をされれば大きな間違いは、無いハズです。
塗料の油性と水性の違い
今回仕上げ塗料として油性を紹介していますが、仕上がりとしての水性との大きな違いは、油性の方が強く被膜を作るため耐久性が違い野外での使用も可能です。
しかし作業性としては水性の方が取り扱い安い面があったりもします。
それがしとしては、油性ニスは特にフローリングや机、椅子などよく擦れる箇所、水性ニスは、棚や装飾品など日頃しょっちゅう擦れない箇所などに使用するのをお勧めしますが最近の水性ニスは、耐久性も優れていて室内で使用であれば水性ニスの選択もありです。
商品により特性も違ったりしますので変わった重ね塗りや塗り合わせの際は、一度試し塗りするを強くお勧めします。

これは私がやっためちゃくちゃな塗り合わせの例です。
水性ステインのウォルナットにブライワックスのウォルナットさらに保護被膜としてラックニスという塗料を用いて仕上げ塗装したものです。
ブライワックスとニスの親和性がまず怪しいです。それにラックニスはよく擦れる場所などには向きません用途が違います。それを机に塗装したため乾いたと思った後この上で熱々の牛丼食べたら即剥げました笑
木材に仕上げ油性ニスを塗装するのに必要なもの
- 油性ニス
- ハケorコテバケ
- バケツorペール缶
- 紙やすり240番 & 400番~600番
この5点は最低限の品質を保つためにもあった方がよいでしょう。
木材に仕上げニスを塗装するのための手順

木材の塗装前の下地処理(事前の着色が無い場合)
まだ塗装もされてない木材にニスを塗る際は、表面が毛羽立ってガサガサしていますので紙やすりの240番で繊維の方向に平行に磨きます。磨いたら木の粉が付きますので拭き取りましょう。
いかに下地処理を丁寧にやるかよって仕上がりの手触り、光沢感が決まります。
しかしながら油性ニスは、非常に被膜を作るのが上手なので最低限目立つ凹凸や毛羽立ちが取れてしまえば綺麗に仕上がってしまう能力を持っています。
木材の塗装前の下地処理(事前の着色が有る場合)
ここでいう事前の着色は、水性での着色を指します。油性と油性で別の商品だったりすると乾いた後でもお互い溶け合いますので品質の保証が出来ません。
特殊な塗料でなければ水性ステインから油性ニスの重ね塗りは可能です。
既に下地に着色をしてあって木材の毛羽立ちが特に気にならないようであればこのステップを飛ばしてしまって問題ありません。
毛羽立ちが気になるようであれば紙やすりの240番で磨きましょう。磨いたら木の粉が付きますので拭き取りましょう。
1回目の油性ニス塗装(アサヒペン 油性ユカ用ニス 半ツヤ)
今回は、アサヒペン床用ニス半ツヤ、バケツ(ペール缶)に塗料を移して塗装していきますが移す前にしっかり混ざるよう缶を振りましょう。容器はプラスチック容器をおすすめします。
金属だとまた使おうとした時錆びてしまって色が移ってしまう事があります。
次にハケですが買ったばかり時は、毛が抜けますので簡単に抜ける毛は、抜いておきましょう。
それでも安いハケだと塗装中にどうしても抜けてしまうのですが…そのままだと当然ですが塗った先に毛が残ります。乾燥した後から除去しても毛の模様が残ります。
乾燥が始まらないうちに除去してしまいましょう。ホムセンでもお徳用万能ハケでは、なくワンランク上のハケを使えば毛の抜けは、劇的に減ります。
もし多少広い面を塗装しますというのであれば私は絶対コテバケをおすすめします。塗装できる速さも段違いですが毛が抜けて塗装面に残ったりません。コテバケを使う際は、コテバケが入る容器を用意しましょう。
油性ニスは、透明やクリアの商品でも塗料に薄っすら茶色がかった色がついてますので下地に白の色などを使っていた場合でニスを厚塗りしすぎると多少茶色が乗ります。気になる方は、薄塗りを心がけましょう。
仕上げ用の油性ニスは比較的粘質あり塗料が伸びにくい性質があります。もし広範囲を塗る又は、塗りづらさ感じる際は、ペイント薄め液を使って希釈しましょう。希釈する割合は、商品によって様々ですが大概5%~10%のようです。
下は、薄め液になります。油性ニスで塗装したハケやコテバケは、薄め液で油性分を溶かして洗浄します。
塗り始める際は、ハケやコテバケに水気が全くない状態で始めましょう。凄く大事です。
私は水性塗料を使ったコテバケをしっかり洗い再度使用した際、乾燥しきってない状態で塗装を行ったら表面に気泡のようなものが出てそのまま固まってしまいました。
見た目も最悪です。こうならないよう十分ハケ、コテバケは乾燥させましょう。

塗る場所によっては、限界はありますが塗装の際は、なれべく風が無い場所、虫が入ってこない環境を作りましょう。乾燥した時、虫、チリゴミがくっついてると悲しくなります。
下の記事では、塗装の様々な失敗集をまとめてあります。塗料の相性やニアミスによる失敗例が分かります。
1回目塗装後の中間の研磨
乾燥時間は、商品により差がありますが商品の裏に乾燥時間が記載してあります。この時点での手触りは、多少木材の間隔が手に残る程度が理想でしょう。
しっかり乾燥したら紙やすりは400番前後で研磨します。尚中間の研磨を行うと浮き上がってきたほこりや気泡などを除去する役割があります。
磨いたら塗料の粉が残りますの拭き取りましょう。水ぶきをする際は、乾燥するのをしっかり待って2回目の塗装を始めます。
2回目の油性ニス塗装(アサヒペン 油性ユカ用ニス 半ツヤ)
2回目の塗装は、1回目と違って塗った場所が見えづらくなるのでどこから塗ってどこまで塗りきるか
整理してから塗りましょう。
乾燥した際、塗装のつなぎ目や部分的に厚塗りになってしまうと光の加減で目で見えます。ちょっと難しいのですが均一に塗れるよう心掛けましょう。
この塗装が終われば完成です。しっかり塗装できればツルツルのテカテカになっているはずです。もしも塗り足りないかなと感じたら乾燥後重ね塗りも可能です。
広範囲を塗る際には、塗料が不足する場合があります。慣れないと商品に記載してある塗り㎡では、おそらく足りなくなってまた再度購入してくることとなることがありますが必ず同じ商品を使うのを絶対お勧めします。

上の商品は1.8L入りで標準塗り面積(2回塗り)10.8~19.3㎡と記載してありますが10.5㎡をテカテカにするのに1缶では、一回塗りしかできずもう一缶買いたしました。
様々な要素が絡み合ってトラブルが起きた際、何が原因でそうなってしまったのか把握しづらい、頑張って作り上げた作品が最後の最後ダメになってしまうのは、精神衛生上非常に良くないです。(体験済み)
下は、様々な塗料の色見本の記事になります。これから塗料を選ぶ際は、参考にどうぞ!
更にこれらのサンプルが特定の条件下で2年間経てどうなったかの記事は、こちらになります。
下の動画はフローリングに水性ステインで着色した後更に絵を描いて油性ニスで保護したものになります。興味があったら是非ご覧ください。

以上で基本の塗装は終わりです。閲覧ありがとうございました。(謝謝
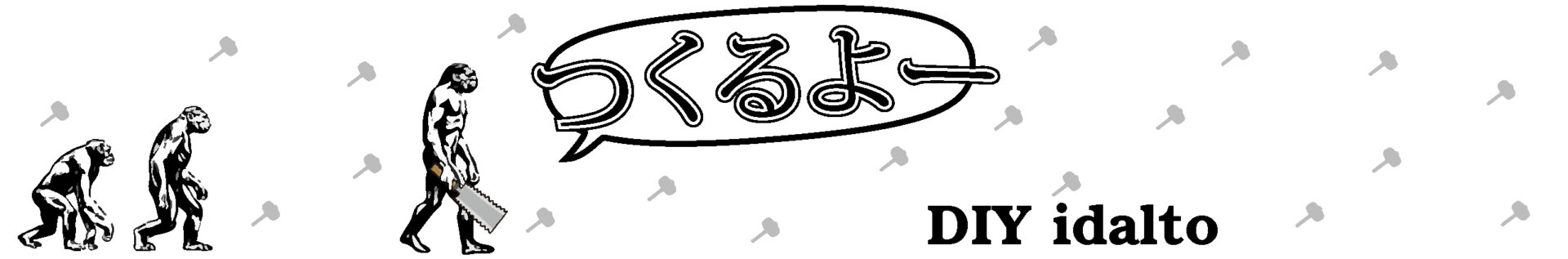





コメント