時にはフローリングに絵を描きたい皆様こんにちは!フローリングに絵を描いてみたイダルトです。
ときに自分の作った作品やフローリングに絵やデザインを描いてみたいと思った方はいませんか?
思いつくだけで具体的な手法や塗料をどれを使えばいいのか考えるのおっくうだったりしますよね~私も色々な作品にデザインしてみたいと思うことがあるのですが水性塗料の兼ね合わせや使うべき塗料なんなのか分からかったのですが実験を含めフローリングに絵を描いた内容などをまとめてみました。
✓本記事のテーマ
この記事を読んでデザインすれば木材の背景に着色、その上に絵を描いて保護塗装することができます。

これら当HPの情報は、管理人が情報を集め徹底的に実践した中での品質、結果になりますので記事を読んで作業をされれば大きな間違いは、無いハズです。
フローリングに絵を描く時必要な物
※1 この塗料に関しては広義で物を指定しにくかったので画像と表現を置いておきます
絵を描く塗料の前置き


絵の部分を描く際はこの2つの塗料を用いました。このメーカーのこの種類の塗料から色を選んでくださいとしたかったんですが都合が良さそうな物がなかったのでこちらの塗料に決定。
木材を塗装する際の手順

フローリングへ塗装前の下地処理
木材の下地処理とは、無塗装の木材の場合、表面が毛羽立ってガサガサしていますので塗装後の肌触り塗りムラが出来ないよう前もってランダムオービットサンダの240番で磨きます。
今回は、無塗装の無垢材に絵を描きますが、既に塗装済みのフローリングの場合は、オービットサンダーやベルトサンダーなで現在ある塗装を除去します。この作業は凄まじい労力を必要としますのでやる場合は相当の覚悟が必要です。
磨いたら木の粉が付きますのでしっかり拭き取ります。下地処理を丁寧にやるかによって仕上がりの手触り、光沢感が決まります。尚きれいに仕上げたい時は、磨く前に霧吹きなどで木を湿らせ乾燥させると更に毛羽が立ちますのでその後磨くと更にきれいに仕上がります。
逆に荒々しいままでよければ下地処理をしなくても塗装できます。仕上がりも相応の仕上がりとなりますが…広範囲の研磨であればランダムオービットサンダというか何らかの電動工具が無いと手のみ作業では中々困難でしょう。
1回目の塗装(背景の塗装アサヒペン水性ステインを使用)
バケツ(ペール缶)に塗料を移しますが移す前にしっかり混ざるよう缶を振りましょう。どの塗料にも言えますが塗料によっては、色味や品質が大きく変わります。容器はプラスチック容器をおすすめします。金属だとまた使おうとした時錆びてしまっていたりして色が移ったりするんですよね~
次にハケですが買ったばかり時は、毛が抜けますので簡単に抜ける毛は、抜いておきましょう。それでも安いハケだと塗装中にどうしても抜けてしまうのですが…そのままだと当然ですが塗った先に毛が残ります。乾燥した後から除去しても毛の模様が残ります。悲しいです。
もし多少広い面を塗装するのであれば絶対にコテバケをおすすめします。塗装できる速さも品質も刷毛より優れています。毛が抜けて塗装面に残ったりもません。コテバケを使う際はコテバケがすっぽり入る容器を用意し専用の容器も売っております。
コテバケにしっかり塗料を染み込ませ、コテバケを容器に押し付けて余分な塗料をしっかり切ります。
繊維の方向に平行に塗装します。塗ってる間に塗料が乾燥してしまいその上を重ねて塗るとその部分だけ色が濃くなります。手早く作業しましょう。
一度の塗装で気に入った色味が出たら塗装を1回目の塗装で終えて問題ありません。
1回目塗装後の中間の研磨
もし1回目の塗装が終わって木材が毛羽立ってしまったら中間の研磨を行いましょう。紙やすりは400番前後がよいです。ランダムオービットサンダだと研磨力が強すぎ折角塗った塗料が剥げてしまいます。
尚中間の研磨を行うと色むらを抑える効果もあります。中間研磨をしたらまた拭き取りを行いましょう。
2回目の塗装(背景の塗装アサヒペン水性ステインを使用)
1回目の塗装と同じく塗装します。2回塗装した方が色むらが気にならなくなります。
デザインをする(絵を描く)
では次に背景色が乗った上に絵を描いていきます。上の写真でいうと白の部分と赤の部分ですね。
絵を描いてから油性ニスで保護塗装されるのであれば必ずこの絵の部分の塗料を水性にして下さい。油性同士だと塗り合わせが悪く仕上がりが凸凹になります。記事の下に凸凹になる動画を貼っておきますので気になる方は、どうぞ
絵のデザインは規則的な箇所綺麗に描きたい箇所は段ボールをくり抜いてその上から塗装しました。法則的でない部分はフリーハンドで!赤の垂れた塗料は、直接ハケからたらしてデザインしてます。


ダンボールの型だと塗料が乾き始めるとすぐに床と段ボールがくっつくので外枠を染めて段ボールを取り上げて中を塗りつぶした方がいいかと思います。そのままにすると床に段ボールが残ります。
尚古い劣化した段ボールより新鮮で丈夫な段ボールの方が綺麗に仕上がります。段ボールの上からいきなり厚塗りすると段ボール側に滲むので薄塗りしてから段ボールを取り上げ後厚塗りした方がよいでしょう。
それでもどうしても滲むかと思いますので多少2~3ミリ小さくした型にしておいて後からハケでラインの修正と塗りつぶしを行った方が綺麗に仕上がります。細かいデザインは、イメージで描きましたスマホにイメージの画像を保存して覗きなら作業すると良いかもしれません。

よく写真を見ると分かりますがダンボールで型を取った箇所が滲んで凸凹になっています。後でアウトラインを太くしてリカバリーしてます。
油性ユカ用ニスで保護塗装をする
最後に保護塗装をしていきますが他の記事にて解説してありますのでそちらをご覧ください。
下に記事を貼っておきます。
動画にてフローリングに絵を描くのをダイジェストしてますのでよかったらそちらもどうぞ
以上で木材に絵を描く!は終わりです。閲覧ありがとうございました。(謝謝
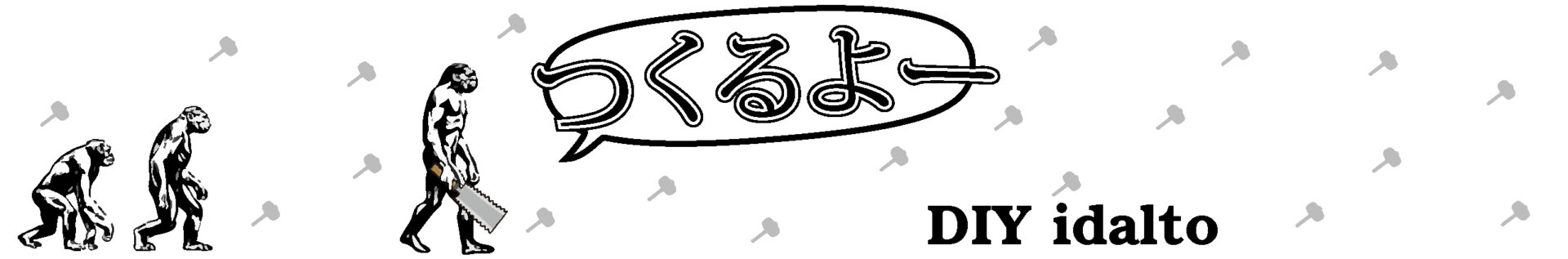





コメント